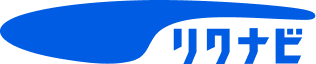証券業界とは、株式・債券・投資信託などの売買の仲介を通して、企業と投資家をつなぐサポートをしている業界です。証券会社の種類や仕事内容、最新の動向や将来性など、就活準備に役立つ基礎知識をわかりやすく紹介します。
証券業界とは
証券業界とは、投資家の資産形成や企業の資金調達を支えている業界です。具体的には、個人や法人の投資家による株式売買を仲介したり、株式発行によって事業資金を集めたい企業をサポートしたりしています。証券取引の仲介を通して、「資金を投資したい側」と「資金を活用したい企業」の間を取り持っている業界といえるでしょう。
なお、近年では少子高齢化による社会保障の先行きへの不安感を背景に、「貯蓄から投資へ」という国民意識が高まっています。株式や投資信託による利益が一定額まで非課税になるNISA制度が注目されていることや、株高(市場全体の株価が上昇している状態)を背景に投資家の売買が活発になっていることも、証券業界にとって追い風です。今後も、国内外の資金の循環を支えていく重要な業界といえるでしょう。
証券会社の種類
証券会社は、主に店舗型とネット型の2種類に分けられます。それぞれの特徴をまとめました。
店舗型証券会社
実店舗や電話、オンラインといった豊富な窓口を介して、個人の株式・投資信託売買や、法人向けの大規模取引をサポートする証券会社です。売買を代行するだけでなく、顧客の投資方針や資産状況に応じた提案も行っている点が特徴といえます。
代表的な企業としては、以下が挙げられます。
- 野村證券株式会社
- 大和証券株式会社
- SMBC日興証券株式会社
- みずほ証券株式会社
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
ネット証券会社
株式や投資信託などのオンライン取引サービスを提供している証券会社です。実店舗や営業拠点を持たないことが多く、店舗型の証券会社と比べて人件費や運営コストを抑えやすいという特徴があります。オンラインから自己判断でいつでも投資できる利便性や、必要なときだけ電話やチャットなどから投資相談ができる安心感、取引手数料(株式の売買に際して発生する手数料)の低さからシェアを伸ばしています。
代表的な企業としては、以下が挙げられます。
- 株式会社SBI証券
- 楽天証券株式会社
- 松井証券株式会社
- マネックス証券株式会社
外資系や中堅・準大手証券
国内の証券会社には、海外の証券会社の日本支社である「外資系証券会社」や、中堅・準大手の証券会社もあります。有名な企業としては、以下が挙げられます。
- ゴールドマン・サックス証券株式会社
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
- 岡三証券株式会社
- 東海東京証券株式会社
- いちよし証券株式会社
- 水戸証券株式会社
外資系証券会社では、法人向けの資金調達や大型M&Aなど、グローバルな金融取引を支援する仕事が中心です。中堅・準大手証券会社は、大手証券会社と比べて規模は小さいものの、地域住民との長年の信頼関係を生かした営業活動で業績を伸ばしています。
証券会社の主な業務
証券会社の仕事は、「ブローカー業務」「ディーリング業務」「アンダーライター業務」「セリング業務」の4つに分けられます。それぞれの内容と役割を見てみましょう。
ブローカー業務(仲介業務)
顧客に代わって株式や債券、投資信託などの注文を市場に取り次ぎ、売買を成立させる業務です。証券会社の基本的な業務であり、取引手数料が収益源となります。主にリテール営業(※1)や法人営業が担当する業務です。
(※1)個人の顧客を対象に資産運用の提案や相談対応を行う職種
ディーリング業務(自己売買業務)
証券会社が自社の資金で株式や債券を売買し、価格変動による差益を狙う業務です。相場の動きによっては損失を被るリスクもありますが、大きな収益を生むこともあります。株価の上昇を狙った買い(ロング)や、下落を見込んだ売り(ショート)など、市場の動きを判断する力が必要です。主にトレーダーが担当します。
アンダーライター業務(引受業務)
企業が新規上場(IPO)や社債の発行を行う際に、証券会社が一部またはすべての株式や社債を引き受け、投資家に販売する業務です。売れ残りが生じた場合は、自社で保有するリスクも負います。主に法人営業が担う業務です。
セリング業務(販売業務)
企業やほかの証券会社から委託を受け、株式や社債などを販売する業務です。販売手数料が収益源で、アンダーライター業務と異なり、売れ残った際のリスクは負いません。投資信託など、顧客の資産運用を支援するサービスもセリング業務の一環です。主にリテール営業や、法人営業が担当します。
証券業界の現状と課題
昨今は物価高や社会保障の先行きへの不安感から、「貯蓄から投資へ」という国民意識が高まっています。しかし、日本証券業協会が実施している「証券投資に関する全国調査」によると、金融商品の保有率は「預貯金」が圧倒的に高く、「株式」「投資信託」はいずれも2割以下にとどまるという結果になりました。「値下がりの危険がある」「十分な知識をまだ持っていないと思った」などの理由から、投資を控えている人はまだまだ多いといえます。
証券会社との取引についても、「敷居が高い」という回答が多く挙がっています。証券業界は堅調に成長している業界ですが、まだ投資に参入していない層をどれだけ獲得できるかが、業界の今後の成長性を左右するといえるでしょう。
業界のそのほかの課題としては、下記が挙げられます。
顧客の高齢化
他業界と同じく、証券業界においても少子高齢化が課題になっています。日本では高齢者層ほど貯蓄額が高いことから、今後は証券会社の主要な顧客層が減っていくことが予想されるためです。
加えて、高齢の方への営業活動にも一定の制限が設けられていることを受けて、今後は若者層の顧客を増やしていくことが今まで以上に不可欠となります。インターネットを介して少額から投資できるシステムや、AIが投資志向に応じた商品を紹介してくれるサポートサービスなど、「専門知識がなくてもシンプルに投資できるようにする仕組み作り」が急がれています。
サイバーセキュリティへの対策
オンライン証券取引が普及する一方で、証券口座の乗っ取りなどの被害も発生しています。口座への不正アクセスや不正取引といった深刻な被害が起こらないよう、しっかりとしたセキュリティ対策が求められているといえるでしょう。実際に多くの証券会社で、ログインに必要な認証システムの見直しや、不正アクセスへの対策が進められています。
証券業界の押さえておきたいトピックス
最後に、証券業界のトレンドトピックスを紹介します。
NISA・iDeCoの拡充
若者層を中心に、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した投資が広がっています。NISAとは、「NISA口座」での投資で得た利益のみ非課税となる制度で、少額から資産運用を始めやすい仕組みです。iDeCoは、自分で積み立てた資金を将来の年金として受け取る制度で、掛け金が所得控除の対象になるなどのメリットがあります。
NISAは2014年、iDeCoは2001年から存在する制度ですが、非課税枠の拡大や対象者の拡充といった制度改正があったことを受けて、資産形成の手段として注目を集めています。
手数料ゼロ化
証券会社の主要な収益源である、「取引手数料」の引き下げ競争が激しくなっています。例えば大手証券会社では、100株(1単元※2)未満の売却にかかる手数料の引き下げや、オンラインサイトからの株式売買にかかる手数料の割引といった取り組みを実施。さらにネット証券の中には、株式取引の手数料をゼロにする企業も出てきています。
(※2)単元とは、株主総会の議決権を1票持つ株の単位のこと。日本では、100株が1単元に統一されている。
こうした動きを受け、証券会社各社は手数料に頼らないビジネスモデルへの転換を進めています。
ESG投資の拡大
「ESG投資」とは、「環境への配慮や社会貢献の意識があり、かつ適切なガバナンス(企業統治)がなされている会社に投資しよう」という考え方のことです。環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の頭文字を取って生まれた言葉であり、投資先を選ぶ際の判断基準として注目されつつあります。
投資先選びにおいて「ESG」が重視される理由としては、ESGを兼ね備えた企業は安定的な成長を遂げやすく、投資リターンも期待できると考えられているためです。ESG投資への関心の高まりを受けて、証券会社でもESG関連商品をPRする動きが進んでいます。
まとめ
投資家と企業の仲介を通して、経済全体の資金循環を支えている証券業界。近年は、NISAの拡充や手数料ゼロ化といった世の中の変化に合わせて、新たなビジネスモデルの模索も進んでいます。業界の転換期にある時期だからこそ、最新の動向や各社の取り組みにアンテナを張っておくことが大切といえるでしょう。
証券業界に関するインターンシップやオープン・カンパニーに興味がある方は、下記ページもぜひチェックしてみてください。

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。