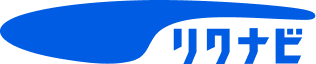出版・雑誌業界とは、書籍や雑誌といった出版物の企画・編集・制作・流通を担う業界です。近年はインターネットやスマートフォンの普及により、電子書籍やデジタル雑誌の需要が拡大しています。業界の概要はもちろん、代表的な企業や仕事内容、最新の動向など、業界研究に役立つ情報を網羅しました。

出版・雑誌業界とは
出版・雑誌業界は、出版物の企画・編集・制作・流通を担う業界です。小説や漫画、雑誌といったさまざまな出版物を企画・製本し、全国の書店などを通じて読者に届けています。
また、近年はインターネットやスマートフォンの普及により、電子書籍やデジタル雑誌の需要が拡大。紙の本と並行して電子版の書籍を配信したり、既存の書籍をデジタル化したりするなどの取り組みも進めています。
出版・雑誌業界のビジネスの流れ
出版・雑誌業界には、「出版社」「編集プロダクション」「出版取次店」「書店」がかかわっています。それぞれの特徴や代表的な企業をまとめました。
出版社:企画から制作を担う中心的存在
出版社は、雑誌や書籍といった出版物の企画・編集・制作を担う企業です。出版物を販売・複製する権利も有しているため、売れ行きがいい書籍の増刷なども担っています。インターネットの普及を受けて、紙媒体に加えてWeb漫画や電子書籍といったデジタルコンテンツに力を入れる企業も増えています。
なお、出版社には漫画や雑誌といったさまざまな出版物を扱う総合出版社と、特定の出版物に特化した出版社があります。代表的な企業は以下の通りです。
■総合出版社
・株式会社講談社
・株式会社集英社
・株式会社小学館
・株式会社KADOKAWA
■特化型の出版社
・株式会社ゼンリン(地図に強い)
・株式会社学研ホールディングス(教材に強い)
編集プロダクション:制作を支える外部パートナー
編集プロダクションは、出版社から依頼を受けて雑誌や書籍、企業パンフレット、Webメディアなどの編集・取材・制作を行う企業です。出版社の編集部が出版物の企画方針を立て、編集プロダクションが制作部分を担当することで、限られた期間で良質なコンテンツを量産できる仕組みを支えています。
場合によっては編集プロダクション側から出版社に企画を持ちかけ、新たなプロジェクトが生まれることもあります。
出版取次店:流通を担うハブ役
出版社から書籍や雑誌といった商品を仕入れ、全国の書店に卸している企業です。「出版社の決めた通りの価格で書籍を市場に卸し、売れ残った書籍を回収して出版社に返品する」という仕組みを取次店が担うことで、書店は在庫を抱えることなく、さまざまな本を仕入れることができます。
また、出版社と電子書籍書店の間に入って取り次ぎを行う「電子書籍取次店」という企業もあります。電子書籍には返品対応や発送作業がないため、代わりにWebマーケティングなどのプロモーションやサイト運営などのサービスを提供することで、事業の拡大を目指しています。
出版取次店の代表的な企業としては、以下が挙げられます。
・日本出版販売株式会社
・株式会社トーハン
書店:読者と本をつなぐ販売拠点
読者に書籍や雑誌を販売する小売り拠点です。店頭での接客やレジ業務だけでなく、売れ行きを踏まえた棚づくりや、新刊の仕入れ判断といった“売り場の編集”の役割も担っています。大型店ではスタッフがそれぞれ専門書や児童書などの担当ジャンルを持ち、地域の読者層に合わせた品ぞろえを考えることも多いです。
また、書店は販売の場にとどまらず、イベントやサイン会、地域情報の発信といった文化拠点として機能するケースもあります。オンライン書店の台頭で購入手段が多様化した一方で、リアルな書店ならではの発見やコミュニティー性は依然として強みとされており、店頭での体験価値を高める取り組みも広がっています。
代表的な企業としては、以下が挙げられます。
・株式会社紀伊國屋書店
・株式会社丸善ジュンク堂書店
出版・雑誌業界の主な職種
出版・雑誌業界にはさまざまな仕事がありますが、どの企業で働くかによって役割が大きく変わります。出版・雑誌業界の主な職種を、「出版社」「編集プロダクション」「出版取次店」「書店」という勤務先ごとにまとめました。

出版社の職種
■編集者
本や雑誌の企画立案から完成に至るまで、一連の制作工程を統括します。複数の企画を並行して動かすことが多く、企画力に加えて、著者・制作スタッフとの調整力が求められるポジションです。
■営業(広告営業・書店営業)
出版社の営業は、大きく「広告営業」と「書店営業」に分けられます。
広告営業は、自社が出版している雑誌などの広告枠を販売するポジションです。コンテンツの読者層や企画特性を踏まえてクライアントを開拓し、最適な掲載プランを提案します。
一方、書店営業は取次店や書店に出版物を取り扱ってもらえるよう、魅力を伝えていくのが役割です。店頭での販売促進のための施策や陳列位置などもアドバイスし、出版物の売り上げがアップするようにサポートします。
■デジタル・IT関連職
電子書籍やデジタル雑誌などのWebコンテンツを、読者に届けるための仕組みづくりを担います。配信システムやアプリの開発・運用を行うほか、紙の出版物を電子書籍として配信できるようにしたり、作品を適切に検索・閲覧できるように作品データを管理したりなど、出版物のデジタル流通を整えるポジションです。
編集プロダクションの職種
■編集者
出版社が決定した企画方針や制作予算を踏まえて、コンテンツの制作全体を進行するポジションです。複数の案件を並行して担当することも多く、クオリティーを保ちながら納期を守る管理能力が求められます。
■ライター
出版社や編集プロダクションからの依頼に沿って、記事の執筆や取材対応を行います。媒体の特性に合わせて文体や情報量を調整しながら、読者に伝わる形で内容をまとめるのが役目です。外部のフリーランスに委託することもあります。
■フォトグラファー
誌面やWeb記事に使用する写真・動画を撮影します。撮影対象は人物・商品・風景など多岐にわたり、編集スタッフやデザイナーと連携しながら、必要なカットをそろえていきます。媒体の雰囲気や企画の意図を理解した上で、最適な構図やライティングを選ぶことが求められます。
■デザイナー
原稿の方向性や読者層を踏まえて、誌面デザインやレイアウトを担当するポジションです。書籍・雑誌・Webなど媒体によってデザインの方向性が異なるため、媒体への理解や表現力が求められます。
出版取次店の職種
■営業(出版取り次ぎ営業)
出版社と書店の間に立ち、商品の仕入れ条件や、書店に卸す書籍数、販売促進のための施策を調整するポジションです。書店での売れ行きや地域ごとの傾向を踏まえながら、出版社には販売戦略を、書店には売り場づくりの提案などを行います。
■物流管理
書籍の在庫管理や入出庫作業、配送手配などを担当します。書籍の刊行スケジュールを理解した上で、大量の出版物を正確に管理することが求められます。
書店の職種
■販売スタッフ
店頭での接客やレジ対応だけでなく、在庫管理、棚づくり、仕入れ発注など、店舗運営のさまざまな業務を担います。読者に最も近い立場で本の魅力を伝えられるポジションです。
■広報・販促
作品やフェアの見せ方を工夫しながら、読者の興味・関心を引き出すポジションです。具体的には、店頭POPの作製やSNSでの情報発信、著者イベント、キャンペーンの企画運営などを通して、集客や売り場の活性化を図ります。
出版・雑誌業界の現状と今後の課題
出版・雑誌業界はマスメディアの一角として、長期にわたって安定的な成長を続けてきた業界です。一方で、昨今は少子高齢化やデジタルコンテンツの登場による余暇時間の奪い合い、本離れ・活字離れといったさまざまな要因により、国内マーケットの縮小が懸念されています。
このような現状を受けて、各出版社では新しい収益源として、人気漫画や人気小説を多角的なコンテンツに成長させる「メディアミックス展開」に注力しています。今後も出版物そのものへの需要を育てつつ、出版物に依存し過ぎないビジネスモデルの構築が進んでいくでしょう。
そのほかの課題としては、以下が挙げられます。
書店は全国的に減少
全国の書店数は年々減っており、中には書店が1軒もしくは存在しないという市町村も珍しくありません。本を売るだけでは採算が取りにくくなっている現状を受けて、顧客の滞在時間を増やすために、カフェや文具エリアを併設する店舗も増えています。
著作権侵害と海賊版問題
インターネットの発達に伴い、海賊版サイトやSNSによる出版物の無断転載が深刻化しています。日本の漫画やアニメといったコンテンツは海外人気も高いことから、無断で翻訳された出版物が海賊版として出回るケースも多いです。政府は国内外の海賊版サイトの規制に力を入れていますが、年間の被害額は数千億円単位にも及ぶのが現状です。
このような現状を受けて、出版業界は国内外で同時にメディアミックスを展開していける市場づくりを急いでいます。版権元である出版社が、全世界で同時にコンテンツを公開することで、収益を最大化することが主な狙いです。
AIの発達によって多国語への翻訳のスピードが格段に上がったことや、海外でも日本の漫画やアニメを流通させる基盤が充実してきたこともあり、今後も全世界同時のメディアミックス展開は続いていくことが考えられます。
まとめ
出版・雑誌業界の特徴や仕事内容、業界の動向などについてご紹介しました。
出版・雑誌業界は活字離れや書店の縮小といった課題を抱えつつも、人気コンテンツのニーズを生かして、デジタル展開やグローバル配信といった新しい挑戦も続けています。出版・雑誌業界に関するインターンシップやオープン・カンパニーに興味がある方は、下記ページもぜひチェックしてみてください。

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。