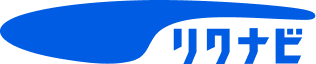化粧品業界とは、スキンケアやメイクアップに役立つ化粧品の企画・開発・製造・販売を手掛けている業界です。化粧品業界のビジネスモデルの特徴や主要企業の強み、職種ごとの役割など、就活準備や業界研究に役立つ情報をまとめました。
化粧品業界とは
化粧品業界とは、スキンケアやメイクアップに用いる「化粧品」の企画・開発・製造・販売を手掛けている業界です。化粧品は日々の身だしなみや美容習慣に欠かせないものであり、生活に根付いているために手堅い需要がある一方で、消費者の趣味や憧れ、ブランドイメージなどが購買行動に影響を与える側面もある業界です。また、消費者の支出が抑制される傾向にある不景気の時期などには、化粧品の消費量が減ったり、比較的安価な商品が選ばれたりするケースもあるため、消費者ニーズや世の中のトレンドなどを踏まえたビジネス展開が求められる点も特徴と言えるでしょう。
| カテゴリー名 | 主な製品例 |
|---|---|
| スキンケア | 化粧水、美容液、乳液、クリームなど |
| メイクアップ | ファンデーション、口紅、アイシャドーなど |
| ヘアケア | シャンプー、コンディショナー、整髪料など |
| ボディーケア | ボディーソープ、ボディークリーム、制汗剤など |
| フレグランス | 香水、ボディーミストなど |
| トイレタリー | せっけん、ハンドソープ、入浴剤など |
また、ひと口に「化粧品」といっても、その範囲は多岐にわたります。具体的には、以下の6つのカテゴリーに分類されることが多いです。
上記のカテゴリーを幅広く手掛ける総合化粧品メーカーをはじめとして、販売・マーケティングに注力する企業や、化粧品の原材料の研究・開発を担う企業など、さまざまなプレーヤーが連携して業界が成り立っています。
化粧品業界のビジネスの流れ
化粧品業界のビジネスは、一般的に以下のような流れで進んでいきます。

研究・開発から販売までを自社で一貫して手掛けているのが、株式会社資生堂や花王株式会社といった大手企業です。研究・製造用の自社工場を持ち、商品の研究・開発や製造、販売チャネルの構築、プロモーション活動までをトータルで担える点が強みといえます。
一方で、中堅・中小の化粧品メーカーは、特定の工程に特化した分業型の企業が多いです。例えば、以下のように特定の領域に注力してビジネスを手掛けるケースが存在します。
OEM企業:製造受託に特化
OEM(Original Equipment Manufacturer)は、他社ブランドの製品を受託製造する企業のことです。「発注元の製品仕様に沿って化粧品を量産する」というビジネスモデルを取ることで、製品の研究コストを抑えながら、自社工場の稼働率を高めることができます。
代表的な企業例としては、株式会社コスモビューティーや株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスなどが挙げられます。
ODM企業:製造+開発も担う
ODM(Original Design Manufacturer)は、製造だけでなく製品の設計・開発までを一括して担う企業です。商品企画や開発に携わることから、高い技術力や企画提案力を発揮できるところが強みといえます。TOA株式会社(旧:日本コルマー株式会社)、株式会社東洋新薬などが代表例です。
なお、ここではOEM企業とODM企業を区分して解説しましたが、代表例として挙げた企業も含め、OEM・ODMを両方手掛けている企業も存在します。
ブランド・販売特化型:マーケティング戦略に注力
化粧品会社の中には、商品開発や製造は他社に任せ、自社はマーケティングやブランド設計に特化している企業も存在します。広告・宣伝やEC販売、顧客分析などを通して、エンドユーザーである消費者に化粧品の魅力をアピールすることに注力できるところが強みです。
代表的な企業としては、株式会社ディーエイチシーや株式会社北の達人コーポレーションなどが挙げられます。
販売チャネルも多様化
なお、近年の化粧品業界は、販売チャネルも多様化しています。百貨店やドラッグストア、訪問販売といった対面・小売り販売はもちろん、インターネット経由の販路も拡大中です。
このように、化粧品業界では企業の規模や戦略によって、手掛けるビジネスの範囲や販売チャネルが大きく異なります。企業ごとの役割や強みに注目することで、自分の志向に合った企業を見つけやすくなるでしょう。
日本の代表的な化粧品メーカー
日本には、国内外で高い評価を受ける化粧品メーカーが数多く存在します。ここでは、売上高やブランド力、製品カテゴリーの幅広さなどを踏まえ、代表的な4社を紹介します。
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| 株式会社資生堂 | スキンケア・メイクアップの両領域でグローバルに展開。高級ブランドから大衆向けまで幅広いラインナップに強み。 |
| 花王株式会社 | トイレタリーやヘアケア分野に強い。医薬部外品や日用品との横断的な商品展開が特徴。 |
| 株式会社コーセー | メイクアップ領域に強い。百貨店からドラッグストアまで、さまざまな価格帯のブランドを複数展開。 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | スキンケア領域に強い。高価格帯ブランドのポーラと、手に取りやすい価格帯のオルビスが中核ブランド。データ活用やパーソナライズにも力を入れている。 |
また、日本の化粧品業界には長年活躍している上記4社のほかにもさまざまなプレーヤーが存在します。
例えば富士フイルム株式会社は、写真フィルムの研究を通して培ったナノテクノロジー技術などを生かして、化粧品事業へ参入しました。さらに、マーケティングやブランディングを強みに、新たにヘアケア・ボディーケアに参入した株式会社I-ne(アイエヌイー)なども存在します。
このように、化粧品業界は大手の老舗だけでなく、異業種からの参入企業や、独自の戦略で存在感を高める企業も交えながら成長を続けている業界だといえるでしょう。
化粧品業界の主な職種
化粧品業界では、商品が企画されてから消費者に届くまでのプロセスの中で、さまざまな職種が活躍しています。代表的な職種を簡単にまとめました。
商品企画職:製品コンセプトを形にする
市場動向や消費者ニーズを踏まえて、新製品の企画や方向性を立案する職種です。トレンドの分析や市場調査を基に製品のコンセプトを練り、研究・開発部門と連携しながら、具体的な製品化へとつなげていきます。
研究・開発職:技術と品質維持の中核を担う
市場のトレンドを踏まえつつ、安全性の高い良質な製品を開発します。化粧品のプロトタイプを作り、何度も品質検査を行いながら、魅力的な化粧品を作っていくのが役目です。
生産・品質管理職:安定供給を支える現場
化粧品の生産や、品質の管理に携わります。現場での技術力と管理力が求められるポジションです。
マーケティング職:顧客心理を読み解く
化粧品のプロモーションやイベントを企画するポジションです。従来は「消費者の心理を読んだ上で、ブランドの価値をPRする」という役目が主でしたが、近年は購買層の消費行動や反応をリアルタイムに収集しながら、より消費者層のニーズに沿ったアプローチを行うことが可能になりました。データに基づく分析と、ブランドの世界観をどう伝えるかという感性の両立が求められます。
営業・販売・美容部員職:ブランドを届ける最前線
店舗や取引先にて、ブランドの魅力をお客さまに伝える役割を担います。実際に自社製品を用いて提案を行うため、美容に関する専門知識に加えて、相手の魅力を引き出すメイクアップスキルやアドバイス力が求められるポジションです。
化粧品業界の現状と今後の課題
化粧品市場は国内・輸出とも伸長傾向にあり、コロナ禍の収まりを経てインバウンド需要も回復しています。アジア圏内を中心とする海外への輸出も伸びているなど、堅調な成長を続けている現状です。メンズコスメやエイジングケアといった新しい市場の開拓も進んでおり、引き続き成長が見込める業界といえるでしょう。
また、インターネットの発展により、化粧品業界の販路も大きく変化しています。従来は対面販売や小売り販売が主流でしたが、最近は独自のEC販売サイトを持つ化粧品企業も増え、実店舗とインターネット双方から集客を狙う「オムニチャネル化」も活発です。そのため、テレビや雑誌、店頭でのPRなどだけでなく、ECサイトを魅力的に作り込むことや、動画サイトや、SNSなどインターネット上での露出もますます重要になっています。
化粧品業界が抱える課題
一方で、化粧品業界には下記のような課題もあります。
- 人口減少による国内需要の低下が懸念される
- 海外における日本ブランドの化粧品の存在感が、まだ十分に確立されていない
化粧品業界も他業界と同じく、国内の人口減少に伴って、国内市場が縮小していくことが予想されます。そのため、海外展開に力を入れる企業も増えていますが、グローバル市場における日本ブランドのシェアはまだ拡大の余地が残されている状況です。理由としては、日本と海外では化粧品に対する文化や規制などが異なる点が挙げられます。
例えば、日本のスキンケアは保湿を重視する傾向にありますが、海外のスキンケアは角質を除去する用途で使われることが多いなど、国によってスキンケアの文化も異なります。売れ筋のメイクカラーなども国ごとに異なります。また、法律によって化粧品に使える成分が規制を受けるケースも存在します。海外展開を進めるに当たり、国ごとの化粧品のニーズをくみ取ることや、規制を理解して各種手続きなどの対応を行うことが課題といえるでしょう。
化粧品業界の注目トピックス
最後に、就活準備の際に知っておきたい業界のトピックスをまとめました。
パーソナライズ化粧品
個人の肌質に合わせてオーダーメードのスキンケア用品を提供する、「パーソナライズ化粧品」の市場規模が拡大しています。AIなどの技術発展により、店頭で肌診断サービスを提供できるようになったことも追い風となり、2020年3月には韓国ではパーソナライズ化粧品制度が施行されました。世界市場でも注目が高まりつつある商品といえるでしょう。
メンズ化粧品の躍進
近年は若年層を中心に「清潔感」や「身だしなみ」への意識が高まっていることを受けて、メンズ化粧品の市場規模も年々拡大しています。特に洗顔やクレンジング、美容液といったスキンケア商品の売り上げが伸長しており、新たな成長分野として男性向けの製品ラインを立ち上げる動きも活発です。
クリーンビューティー
クリーンビューティーとは、人体や環境に悪影響がある成分や刺激物が使われていない、安全に配慮されているなどの特徴を重視する考え方や、そのような考え方に基づいて作られた製品を意味します。化粧品は「その人の思う美しさ」や「健やかさ」を引き出す商品であることから、各メーカーは健康を害するような製品が世に出回らないよう、細心の注意を払って製品開発を行っています。世界的に環境意識やSDGsへの関心が高まっていることも受けて、今後も「クリーンビューティー」な製品作りが求められていくでしょう。
まとめ
化粧品業界の概要や業界の仕組みなど、業界研究に役立つ基礎知識をご紹介しました。化粧品業界とひと口にいっても、企業ごとにビジネスの流れや得意とする工程が異なります。業界の将来性や課題、注目トピックスを踏まえて調べることで、各企業への理解が深まるほか、自分にとって興味を持てそうな仕事も見つかりやすくなるでしょう。
化粧品業界に関するインターンシップやオープン・カンパニーに興味がある方は、下記ページもぜひチェックしてみてください。

東京工業大学(現:東京科学大学)大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。