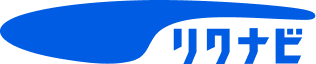目次
(1)ドラッグストア・医薬品・化粧品・調剤薬局業界の概況
医薬品は、大別すると、医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」と、処方箋が不要な「一般用医薬品」の2つに分けられる。一般用医薬品は大衆薬、市販薬、OTC医薬品(Over The Counter:オーバー・ザ・カウンターの略で、カウンター越しに薬を販売することからついた名称)などとも呼ばれる。
さらに一般用医薬品は、含有する成分などによって要指導医薬品、第1類・第2類・第3類の4つに分かれ、要指導医薬品と第1類医薬品の販売には、薬剤師からの情報提供や指導が義務付けられている。
店舗単位でみてみると、主に一般用医薬品を扱うドラッグストアと、医療用医薬品を扱う調剤薬局との2つの店舗に分かれる。
ドラッグストアは、一般用医薬品や化粧品、最近では食品や飲料など、幅広い商品を取り扱っている。ドラッグストアが日本で最初に登場したのは1970年代。それが2016年には約1万8000店舗にまで増え、売り上げ規模は6兆円を超えている。2000年以降、各社は店舗数を急速に拡大し、過去15年間で約5割増となった。ただし、ここ数年の成長率は鈍化傾向にあり、市場は飽和状態を迎えつつある。近年は、大手企業がM&Aをしかけるなどによって業界再編が進み、企業数は減少傾向。大手企業の中には、売上高が5000億円台に達するところも現れた。
調剤薬局は、保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い、調剤を行う薬局の通称。薬剤師のいる薬局数は全国で5万8000カ所以上あり、個人経営型の薬局と、大手調剤薬局チェーンの二極化が進んでいる。調剤は、国の医療政策による薬価価格の変動(引き下げ)など、国の医療費削減の施策が大きく影響するため、調剤部門だけでは経営の安定性を保ちにくい。そこでドラッグストアのように一般医薬品や化粧品など、幅広く取り扱うなどして、収益源を多様化するケースや、大手調剤薬局チェーンではM&Aによって企業規模を拡大し、経営の効率化に努めたり、より採算性が見込まれるエリアに新規出店したりする動きが盛んだ。
(2)ドラッグストア・医薬品・化粧品・調剤薬局業界の仕組み
ドラッグストアの売り上げの内訳は、医薬品が3~4割を占め、化粧品が2割、日用雑貨が2割、食品…と続いている。また、店舗の立地や規模によって商品やサービス構成はさまざまであり、中には調剤薬局を併設するドラッグストアも増えている。
近年では、医薬品の販売に対する規制緩和の動きを受け、ドラッグストア以外にも、インターネットやコンビニエンスストアで一部の医薬品を販売することができるようになった。取り扱い店舗数が増えたことで、競争は厳しくなっている。
そこで各社は、医薬品以外にも食品や飲料をスーパーマーケットよりも安く販売するなどして、消費者の来店頻度を高めようと工夫している。
一方、訪日外国人が増えるにつれ、彼らの「爆買い」が話題になった。訪日外国人に対する消費税免税制度が改正され、化粧品などが免税の対象になったことも追い風となった。海外、特にアジアの国々では日本製品の品質の高さは有名で、ことに直接肌に触れる化粧品やおむつ、経口服用する薬などにおいて、人気は高い。今後も、こうしたインバウンド需要(訪日外国人の消費によってもたらされる需要のこと)の取り込みは大きなテーマであり、訪日外国人に向けた商品をそろえる、外国語の対応ができるスタッフを雇用するなどの対策が図られるだろう。
(3)ドラッグストア・医薬品・化粧品・調剤薬局業界のHot Topics
スイッチOTCの増加
もともと医療用医薬品として使われていた成分を一般用に切り替えた薬「スイッチOTC」(解熱・鎮痛剤のイブプロフェン錠、ロキソニン錠などが代表格)が増えつつある。自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする「セルフメディケーション」の推進は国も後押ししており、2017年1月からスイッチOTC薬について、医療費控除の特例をスタートさせている。
かかりつけ薬剤師・薬局制度が始動
医療費の削減を推進するために、2016年4月に本格的にスタートした制度。自宅や職場に近い「かかりつけ薬局」の薬剤師が、薬の重複や危険な飲み合わせの防止、患者の健康管理などの相談にも乗る。そして、かかりつけ薬剤師であることを示す同意書に患者がサインをすると、薬剤師は服薬サポートなどを行った場合、毎回一定の指導料を算定できる。
(4)関連業界とのつながり
化粧品メーカー
ドラッグストアの売上構成の2割以上を占めるのが化粧品である。大手ドラッグストアチェーンには、化粧品メーカーの販売員が派遣されているところも少なくない。
専門商社(医薬品)
医薬品を専門に扱う商社(医薬品卸とも呼ばれる)は、医薬品メーカーから仕入れ、病院・診療所・調剤薬局などに卸している場合が多い。医薬品卸は再編が進み、日本医薬品卸売業連合会の会員企業数は1997年には277社あったが、2016年には79社に再編統合されている。
病院・診療所
調剤薬局は医師の処方箋に基づいて、薬を調合する。診療科目や規模に合わせた薬をそろえやすく、患者の利便性も高くなるため病院・診療所の近くに店舗を構える調剤薬局は多い。
▼2026年卒向け詳細情報▼
簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。
インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!
——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー
東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
——————————————————
※記事制作時の業界状況を基にしています
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。