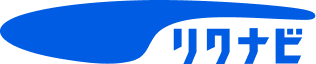(1)鉄道業界の概況
鉄道会社は、人やモノを運ぶ移動手段としての鉄道を維持・運行している企業だ。また、多くの人々が集まる「駅」を基点とし、不動産、小売業、ホテル、レジャー施設といった事業を運営しているところもある。
大手私鉄16社の2016年3月期における総売上高は、前年より1.2パーセント増の7兆7673億円。東日本大震災などの影響もあり、ここ10年で最低の売上高となった2012年3月期(7兆960億円)に比べると9.5パーセント増えた。また、東日本旅客鉄道(JR東日本)と東海旅客鉄道(JR東海)が過去最高の売上高と当期純利益を上げるなど、鉄道各社の業績はおおむね好調だ。
その原動力となったのがインバウンド需要(訪日外国人の消費によってもたらされる需要のこと)だ。訪日外国人が増えたことにより、観光需要が都市部から郊外へ波及し、鉄道会社の運営するホテルやレジャー施設、駅ビル内の商業施設はにぎわいを見せている。ただし、2016年以降、訪日外国人の1人あたりの支出額が減少し始めているというデータもあり、今後はやや不透明だ。さらに、これから少子高齢化によって人口減少が進み、通勤・通学で電車を利用する層が減るのではないかと懸念もされている。
そこで各社は、自社路線の利用者を増やそうと努力を重ねている。キーワードは、「沿線価値の向上」。鉄道路線の周辺地域を、住民が安心して長く住み続けたくなる「価値の高い場所」に変えることで、鉄道をはじめとする自社サービスの利用者を確保しようという考えである。例えば、鉄道会社が沿線エリアで保育所を設立したり、高齢者事業に力を入れたりして、子育て世代やシニア世代が住みやすい街づくりを目指すケースもある。
拠点駅の集客力向上も、大きな焦点となっている。例えばJR東日本は、国土交通省と共に整備した「バスタ新宿」を2016年4月に開業。さらに、商業施設や保育所、クリニック、多目的ホールなどが入居した「JR新宿ミライナタワー」をオープンするなどして新宿の利便性を高めている。また、名古屋市では鉄道会社も参加して「名古屋駅周辺エリアにおけるトータルデザイン検討会議」が開催され、駅前広場などの再開発を議論している。このように拠点駅周辺の環境を整備することで、鉄道利用者の増加や、駅ナカの販売施設の売り上げアップなどを図ろうとしている。
(2)鉄道業界の仕組み
鉄道会社は経営母体によって、日本国有鉄道に起源を有する「JRグループ各社」、民間企業によって運営されている「私鉄」、地方公営企業や地方自治体が運営する「公営鉄道」、国や地方自治体と民間が共同運営する「第三セクター鉄道」の4つに分かれる。また、運ぶものが旅客(=人)か貨物(=モノ)かで分けることもできる。貨物列車は、JRグループの「日本貨物鉄道(JR貨物)」が大半を占めるが、私鉄や専用鉄道も少数ではあるものの貨物を扱っている。
鉄道会社にとって、最も大きな収入源は運賃収入である。しかし、それ以外の売り上げも決して小さくない。例えば、JR東日本の場合、2016年に運輸業(鉄道、モノレール、バス、車両製造事業など)から得た収益は、全体の68.2パーセントだった。一方、駅構内の売店や商業施設などの「駅スペース活用事業」は13.9パーセント、駅近くのショッピングセンターや複合型オフィスビルの「ショッピング・オフィス事業」は8.9パーセント、電子マネーやホテル業などの「その他」が9.0パーセントを占めている。今後は人口減少が進むため、運賃収入が飛躍的に伸びることは期待しづらい。鉄道各社は、運賃収入以外の分野に力を入れて収益アップを目指している。
(3)鉄道業界のHot Topics
相互乗り入れの拡大
異なる鉄道会社同士が互いの路線で車両を運行する「相互乗り入れ」が拡大。乗り換えをせずに目的地まで行けるため、地域住民に住みやすい環境を提供し、沿線価値の向上につなげられる。また、旅行者を観光地に誘導する効果も高いとされる。
「鉄道システム+街づくり」を輸出
日本の鉄道を、車両などの「ハード」と、正確・安全に運行するためのノウハウといった「ソフト」を一緒に輸出する機会が増えている。加えて近年では、鉄道会社が海外で沿線の開発などを含めた街づくりを行うケースも登場。
駅ナカ、駅チカの開発は依然活発
駅ナカ、駅チカの商業施設は高収益が見込めるため、鉄道各社は開発に力を入れている。2017年以降は、横浜(神奈川県)、川崎(神奈川県)、さいたま(埼玉県)、千葉(千葉県)、渋谷(東京都)などの各駅で、駅自体の大改装や周辺商業施設・オフィスビルの開発事業が予定されている。
新型車両の開発も引き続き進んでいる
鉄道各社は、以前から新型車両の開発を進めている。近年では、案内ディスプレイの多言語化・大型化を進めた車両、車内で無線LANサービスを提供できる車両、軽量化や新型モーターの採用で省エネを実現した車両、などが導入された。
(4)関連業界とのつながり
地方自治体
沿線にある観光資源を地方自治体と共に発掘・開発したり、観光客の誘致などで協働したりするケースが増えそうだ。
百貨店
駅ビルに自社傘下の百貨店や、さまざまな小売店を入居させることで、近隣の百貨店と競合関係になるケースもある。一方、鉄道会社と百貨店が合弁会社を作って協力するケースもある。
重工メーカー
鉄道車両の製造、運行システムの構築などで、重工メーカーとは密接な関係にある。海外に鉄道システムを輸出する際にも協力する。
▼2026年卒向け詳細情報▼
簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。
インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!
——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー
東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
——————————————————
※記事制作時の業界状況を基にしています
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。