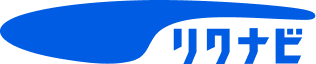(1)教育業界の概況
教育業界には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの教育機関のほか、就学期の子どもを対象とした学習塾・予備校などの学習支援機関、社会人を対象にした語学・資格スクールやカルチャースクール、企業向けの社員研修を扱う企業など、幅広い企業がある。
新型コロナの流行で、微増傾向だった市場規模が縮小へ
学生・未就学児向けの教育関連サービスは、少子化の進行によって顧客の絶対数が減っていくことから、厳しい状況に置かれているものの、業界各社は、より手厚い教育内容や新サービスを開発・提供することで、子ども1人当たりへの支出を高めるように努めたり、社会人を対象にした企業向け研修サービス市場や、資格取得学校市場を強化したりしてきたことで、ここ数年の市場規模は微増傾向が続いていた。しかし、2020年度は新型コロナウイルスの流行の影響を受け、市場規模は前年度に比べ縮小した。
リモート型サービスが伸長
2020年3月以降、政府から学校の休校要請が出されたことを受け、学習塾・予備校においても休塾・休校措置を行うケースが発生。それによって減収や、生徒募集活動の抑制による新規入塾・入校生の伸び悩みなどのマイナス影響が生じた。
その一方で、対面型の教育関連サービスを提供できない状況が続いたことで、オンラインを活用するリモート型サービスの開発・提供に注力する傾向が拡大。社会全体がテレワーク・リモートワークを推進する流れとなったことにより、リモート型サービスに対する抵抗感が薄れたこともあり、コロナ禍でも売り上げを拡大する事業者も存在している。
コロナ禍の影響で、政府による「GIGAスクール構想」が急速に進んだ
コロナ禍前から、時流に合わせて教育にITを活用する動きは進んでおり、政府は「GIGAスクール構想」として、1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、教育現場におけるICT環境の実現を目指す方針を掲げていた。公立の小・中学校では、文部科学省が取りまとめた『教育の情報化ビジョン』(2011年)に基づき、タブレット・ノート型端末の導入が進められていたが、文部科学省による『端末利用状況等の実態調査』(2021年7月末時点)では、全国自治体等のうち、96.1%が端末を整備済みと回答している。全国の公立小学校等の96.1%、中学校等の96.5%が、全学年、または一部の学年で端末の利用を開始している状況だ。コロナ禍の影響から、オンラインと対面の授業を並行できる環境づくりが進んだことがうかがえる。
学習塾・予備校、大人向けサービス、企業向け研修などもオンライン化
一方、学習塾などでもタブレット端末を使った授業は珍しくなくなっている。タブレット端末では、生徒一人ひとりの進度に応じた学習内容の提供が可能となる、生徒の操作に応じてリアルタイムで画面上に新たな追加情報を提示できるなど、双方向なやりとりが可能となるメリットがある。また、オンライン授業が一般化したことにより、首都圏の大手学習塾・予備校で、地方や海外在住の生徒に向けてオンライン授業を提供するサービスを新たに立ち上げる動きもある。
学習塾・予備校の分野では、低価格帯のオンライン授業サービスが登場し、対面授業を中心とする既存の学習塾・予備校にとって脅威となっている。こうした競争環境を背景に、各社ますます、コンテンツのIT化や授業の魅力を高める工夫を凝らしていくと考えられる。また、デジタル教材に関しては、AI(人工知能)技術を活用して、個々の学力や学習進度、理解度などに合わせ、より効果的・効率的な学習指導サービスを提供する動きが活発化し、関連サービスを開発・導入する事業者が急増している。
英会話・語学以外の習い事でもオンライン授業を導入
大人向けサービスの分野では、昨今のグローバル化の流れを受け、英会話・語学スクールはインターネットを使った多様な受講スタイルのサービスが台頭し、既存の通学スタイルの英会話スクールのライバルとなっていた。コロナ禍以降は、音楽教室など、そのほかの習い事分野においてもオンライン授業を取り入れるスクールが増え、オンラインのカルチャーセンター事業に乗り出す企業なども登場している。
資格・検定試験市場では、会場試験の中止が相次ぎ、受験回数の減少によって大きなマイナス影響が及んでおり、一部の試験では、自宅で受験できるオンライン受験のシステム導入をするケースもあった。
コロナ禍で実施機会が減った社員研修もオンラインに活路を
ビジネスの現場では、コロナ禍以前には、社員の即戦力化や業績アップを目的とした企業向け研修サービスなどを堅調に伸ばしてきたが、2020年度は緊急事態宣言が発出された時期に、新入社員研修の実施時期が重なり、中止・延期に追い込まれた。また、こうした状況が階層別社員研修などの実施機会の損失にもつながった。現在、オンラインを活用した研修などコロナ禍に対応した研修サービスへの移行が加速しており、これらのサービス展開によってマーケットが回復している分野も多く見られるため、今後は、再度成長に向かうことも予測されている。
(2)教育業界の仕組み
近年、少子化という大きな課題の下、学習塾・予備校市場では、他社との合併や提携を目指す動きが活発化していた。その狙いの一つは「より早い時点で生徒を取り込むこと」。例えば、大学受験向けの予備校が、小・中学生向けの補習塾などを買収することで、長期にわたって自社の教育サービスとの親和性を高め、同じ生徒にずっと利用し続けてもらうことを目指している。また、関東の企業が関西の企業を買収するなどして、営業エリアを広げて売り上げ拡大を目指しながら、経営の効率化を追求する例もあった。対象となる生徒の年齢・地域を広げるサービスの拡充を目指すこの合併・提携の動きは、現在、一区切りがついた状況となっているが、今後、デジタル教材の活用などと関連して、業界内にとどまらず、IT業界などの他業界も含めた合併・提携が生じる可能性もある。
教育業界全体においては、授業方法の変化が顕著だ。コロナ禍の影響により、従来の対面授業から、オンラインでの遠隔授業を実施する割合がますます増えてきている。
(3)教育業界のHot Topics
授業内容や入試など、学校運営にかかわる文部科学省の方針が変わると、教育業界にも大きな影響を及ぼす。2020年度には、小学校におけるプログラミング教育の必修化や、大学入学共通テストの実施などの大きな変化があった。
また、近年は、アクティブ・ラーニング(能動的な学習)を重視する傾向となっている。教える側が一方的に講義を行うのではなく、ディスカッションやプレゼンテーションなどを通じ、学ぶ側が能動的・主体的に参加するスタイルの授業形態だ。2020年度以降、文部科学省による改定学習指導要領がスタートしたが、こちらにもアクティブ・ラーニングが盛り込まれている。そのため、アクティブ・ラーニングにかかわる教材・学習システムへのニーズも、今後ますます高まるとみられている。
小学校におけるプログラミング教育の必修化
2020年度から、小学校におけるプログラミング教育が導入され、今後中学校、高等学校でも必修化が決定している。プログラミングそのものを学ぶことが目的ではなく、「プログラミング的思考」を育むことに主眼を置き、論理的思考を身につけられる教育を目指す。プログラミング教育への関心が高まり、学習塾などでプログラミングコースを導入するケースが増え、新規参入にて子ども向けにプログラミングやロボットプログラミングを専門に教える教室も急増した。プログラミングは一つの習い事のテーマとなりつつあり、今後、さらなる市場拡大に向かうことが予想される。
また、2020年度には公立小学校において中学年(3・4年生)を対象に「外国語活動」が必修化され、高学年(5・6年生)を対象に正式な教科として「外国語(英語)科」の授業が始まっている。「読む・聞く・書く・話す」に加え、英語で議論・交渉する能力を身につけることも重視される傾向。子ども向け英語教育市場も、プログラミング教育と同様、今後、拡大していくことが予想される。
大学入学共通テスト
2021年1月より、大学入試センター試験に代わって、「大学入学共通テスト」が実施された。出題はマーク式だが、より理解の質が問われ、「思考力」「判断力」を発揮して解くことが求められる問題内容へと変化している。学習塾や予備校はすでにこうした動きに対応しているが、日本の教育そのものがアクティブ・ラーニングを重視する傾向となっており、能動的・主体的に学ぶ流れとなっていくことが予想される。
STEAM教育の推進
アメリカ発祥の「STEM(ステム)」は、ハイテク分野の研究開発に欠かせない教育分野のことだ。「科学」(Science)、「技術」(Technology)、「工学」(Engineering)、「数学」(Mathematics)の頭文字を取った名称だ。近年は、デザインやリベラルアーツ(Arts)の要素が加えられて「STEAM(スティーム)」へと発展し、理系人材の育成のみにとどまらず、理数教育に創造性教育を加えた教育理念として注目されている。
文部科学省では、「AIやIoTなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日、文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められています」とし、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習を推進していく方針を発表している。
海外ボーディングスクール
グローバル化の流れが進み、国も外国語教育に注力する中、欧米の全寮制私立学校、ボーディングスクールが注目されている。数年前より、中学・高等学校から欧米のボーディングスクールに留学し、そのまま海外名門大学に進学してグローバル人材へと育成する流れが一つのトレンドとなっており、大手予備校グループではボーディングスクールへの進学サポートを専門とする海外事業も立ち上げている。
リカレント教育
近年、学校教育から離れた後も、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくことが重要視されている。社会人になっても生涯学び続けることを「リカレント教育」と呼び、国もこれを推進・支援している。大学や公的機関を含め、大人やシニア層に向けた教育サービスの提供を進めていく流れがある。
(4)関連業界とのつながり
IT系企業(情報システム系)
多くの教育系企業が、タブレット端末向け教材や学習アプリの開発を進めている。また、インターネットを活用して授業を行うケースも増加傾向にある。また、ITに注目が集まっているこの十数年の間に、大手IT系企業が文部科学省から認可を受け、通信制の大学や高等学校の運営に参入する動きも出てきている。IT需要を満たす学びのカリキュラムと、ITを活用した柔軟な教育環境を提供できる強みがあり、異業界から参入した新たな競合と言えるだろう。
ゲームメーカー
携帯ゲーム機やスマートフォン向けの学習・知育アプリを開発する企業は少なくない。また、ゲームのように人を楽しませるノウハウは、教材づくりにも役立てられるだろう。
出版社
教育系企業の中には、出版部門を運営して参考書や学習書を販売しているところもある。また、出版社と協力して教材を開発するケースもある。近年はデジタル教科書のコンテンツ化を進める企業も出てきている。
▼2026年卒向け詳細情報▼
簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。
インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!
——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー
東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
——————————————————
※記事制作時の業界状況を基にしています
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。