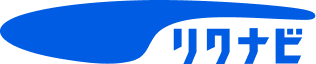公社とは
ここでは公社とは、公益社団法人や公益財団法人、独立行政法人など、私的な利益を追求するのではなく、公(おおやけ)、つまり社会のために存在している組織・団体を指す。かつて中央官庁が担当していた事業のうち、一定の事務・事業を分離し、業務の質の向上や活性化などを狙って設立された独立行政法人も公社の一つと言える。
それぞれの設立目的は以下のように整理できる。
- 公益社団法人…公共の利益を実現するために作られた法人
- 公益財団法人…財産の運用を目的として作られた法人
- 独立行政法人…組織の業務効率や専門性を高めることを目的に、中央官庁から独立して生まれた法人
公益性の高い事業を進めるため、任意団体が法人格を取得して、公益社団法人や公益財団法人となるケースが多い。
なお、公社の場合は一般企業と同様に就職活動を行う必要がある。
公社の今後の展望
公社は、中央官庁や地方自治体と同様に公的な業務を手がけながらも、組織としては企業のような形式を取っていることが多く、「官と民の中間」のような存在と言えるだろう。一般に、公的な官の組織は民間だけでは充足されないサービス(警察・消防、道路・上下水道・公共施設などの整備・運営など)を担う役割を持っている。一方で、近年は「民間でできることは民間に任せる」という流れが進んでおり、結果、官と民の中間の立ち位置である公社が活躍するシーンが増える可能性がある。また、公的な予算の範囲でビジネスを行うだけでなく、自ら顧客獲得や売り上げアップを目指す動きも増えそうだ。
公社のHot Topics
ガバナンスの強化
内閣府は「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」を開催し、2020年12月には、「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(最終とりまとめ)」を公表した。公社は税制の優遇や、寄付等の社会的支援が得られることから、しっかりとしたガバナンス(組織運営のための統治・管理体制)を実現することが求められている。近年、民間企業におけるガバナンス強化に注目が集まっているが、公社についても同様だ。
官庁とは
官庁には、国(中央官庁とも呼ばれる)と地方公共団体(地方自治体とも呼ばれる)などが該当する。これらの、いわゆる「役所」のほか、警察や裁判所などを含むこともある。
官庁で働くには、国家公務員や地方公務員の国家試験合格が求められるケースが多い。
中央官庁
中央官庁には、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省などがある。これらは国の中枢機関として、それぞれの分野で行政をつかさどっている。
中央官庁は、「究極のゼネラリスト組織」と言われる。同じ部署で働く期間が数年間といった場合が多く、人によってはさまざまな部門で経験を積むことができる。幅広いフィールドで仕事をしたいと考える人に適していると言える。
これに対し、権限が特定の地域に限定される組織が地方官庁で、例として税務署が挙げられる。
官庁間での連携もある
中央官庁の役割は、例えば、経済産業省、文部科学省といった各組織がそれぞれ所管する分野について、広範囲に影響する課題を解決することである。なお、課題によっては中央官庁同士が連携することもある。
例えば、経済や産業の発展には技術革新が重要となり、産業界や大学などが連携する「産学連携」の促進が課題となるが、このような場合には経済産業省と文部科学省の連携が必要となる。複雑化する世の中の課題を解決するために、今後も中央官庁が緊密に協力するケースが増えそうだ。
地方自治体
地方自治体は、市町村や特別区などの「基礎自治体」と、都道府県という「広域自治体」に分類される。お互いが役割分担・連携をしながら、その地域に住む人々に対して福祉、保健、教育、警察、消防などのサービスを提供する役割を担っている。ほかにも、更新時期を迎える公共施設や道路などの整備なども、自治体が担う大切な役割だ。
官庁の今後の展望
「働き方改革」「ダイバーシティ」の推進
テレワークの普及など、公務員の働き方改革が進められている。内閣人事局が発表した「令和2年度国家公務員テレワーク取組状況等調査」によれば、テレワーク実施可能職員数は、本省は5万8301人で前年比12%の増加、地方は21万3871人で前年比40%の増加となっている。総務省による「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果」(令和3年10月1日現在)では、都道府県、指定都市では全団体で導入済、市区町村では849団体(49.3%)で導入している。
また、男性の育児休暇取得が推進され、人事院による「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和2年度)」では、一般職国家公務員の男性の育児休業取得率は過去最高の51.4%で、初の5割超えとなった。
ダイバーシティの取り組みの一環として、女性採用の促進も行われている。2020年に策定された第5次男女共同参画基本計画で、国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合を毎年度35%以上に維持する成果目標が定められている。
地方の人口減少への対応
近年、地方自治体を悩ませてきたのが、全国各地の都市圏以外のエリアで進んでいる人口減少問題である。しかし、新型コロナウイルスの流行拡大の影響で、地方からの人口流出が抑制・緩和。これを機に、若者人口や移住者などの定着を目指す自治体が増えている。
人口減少が続くと税収が落ち込み、公共サービスの質が下がったり、地域の活力が失われたりする。すると、さらなる人口流出を招く可能性もある。また、自治体の弱体化が加速すれば、その地域だけで住民向けのサービスを提供することが難しくなることが懸念される。
そのため、公共サービスの効率化の取り組みに注目が集まっており、最近では近隣の自治体同士で、道路・河川の管理、病院や学校の運営、ゴミ処分といった事業に取り組む「広域連携」の動きも出てきている。
地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組み
高齢化による医療・介護の需要の増加と、それに伴う費用増大も、地方自治体にとっては大きな課題となっている。自治体ごとに、高齢化の進展スピード、医療・介護サービスの整備状況、地域コミュニティーの状況などを見極めながら、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を推進していくことが必要とされている。
地域の情報発信の役割
また、これからの地方自治体には、地域のまとめ役・発信役としての役割が求められている。例えば、その地域の観光資源を旅行会社やホテルなどと協力して発掘し、それを地場メーカーやマスコミなどを巻き込みながら全国にアピールして地域の活性化に成功している例は少なくない。自治体で働く人には、情報を積極的に発信する力や、地域住民の中に飛び込んでニーズを聞き、地域の活動をリードしていく力も大事になるだろう。
現在、コロナ禍の影響で、観光産業に主軸を置いている自治体は少なからぬダメージを受けており、税収減少も予測されている。その一方で存在感を増しているのが「ふるさと納税」だ。自治体の税収アップに加え、地域の名産などを返礼品として用意することが地域のアピールとなり、観光・旅行需要の創出や地域活性にもつながることが期待されている。
官庁のHot Topics
中央官庁や地方自治体が何か新しい取り組みやプロジェクトを推進する際、多くの参加者を巻き込んで進める方が波及効果は大きい。そこで、民間企業や、地域住民によるボランティア活動との連携が注目されている。
デジタル化の推進
2021年9月に中央官庁の新組織としてデジタル庁が設置された。マイナンバーカードの活用推進や、国や地方におけるICT利用の活発化に取り組んでいる。また、各種行政機関におけるRPA(※)の取り組みが進んでいる。国民に提供するサービスの向上とともに、行政の業務の効率化も目指す。
※RPA…Robotic Process Automationの略。人間がコンピュータ上で行っていた定型的な作業をコンピュータが代わりに行うようにする取り組み)
デジタル田園都市国家構想
地方からデジタルの実装を進め、地方と都市の差を縮め、都市の活力と地方のゆとりの両方を享受できる「デジタル田園都市国家構想」の実現を図る取り組みが進められている。人口減少の傾向が強く見られる地方部でのデジタル活用を通じ、地方での仕事の場の確保や、教育機会の充実、医療の充実などを推進していく。
地方創生テレワーク
地方においてサテライトオフィスなどでの勤務を可能にし、地方の活性化につなげていく考え方。テレワーク環境を充実させる取り組みを進める地方自治体が登場。コロナ禍でテレワークを希望する就労者が少なからず存在していることもあり、地方に滞在する人は増加傾向となっている。
スーパーシティー・コンパクトシティー実現のための取り組み
スーパーシティー構想とは、地域の課題をITや先端技術を通じて解決する未来都市を目指す取り組みを指す。AIやビッグデータを活用し、社会の在り方を根本から変えるような都市の設計が進められている。例えば、ドローンなどによる自動配送の実現を目指したり、介護や福祉に関するデータを一元化してより良いサービスを受けられるような仕組み作りを行ったり、などの動きが見られる。
また、公共施設や商業施設といった都市機能を、徒歩や自転車で移動できる狭い範囲に集約した街=コンパクトシティーの形成に向けた政策を進める自治体もある。高齢者など車の運転ができない人でも生活しやすい、道路や上下水道の効率が高まるなどのメリットがある。
地域再生法改正案
政府が地域再生法改正案を閣議決定。高齢者の地方移住や地方自治体同士の広域連携などを促進するため、新たな交付金の仕組みを整えている。また、地方自治体に寄付をした企業の税金を軽減する「企業版・ふるさと納税制度」の導入なども盛り込まれた。
関連業界とのつながり
介護・医療
介護サービス事業者や医療事業者と協力・連携し、地域包括ケアシステムを作っていくことが求められている。地域住民に向けた介護や医療におけるサービスの質・量を充実させ、地域全体で高齢社会を支えていく体制を目指す。
旅行・ホテル
地域の観光資源を再発見し、観光客を呼び寄せる取り組みは、コロナ禍で縮小傾向にあるが、多くの地方自治体において「観光産業は、地域における重要産業であること」に変わりはない。ふるさと納税を活用した地域産業のアピールも含め、観光地としてのブランド力向上を図る試みが全国各地で引き続き行われている。
地方銀行
地方銀行は地域経済の要であるとともに、さまざまな地域の情報が流れ込む場所でもある。そこで、地方自治体と地方銀行が協力しながら、地域経済を盛り上げていく必要がある。
シンクタンク
中央官庁から依頼を受けて政策検討に必要な情報・資料の収集や、政策立案に必要な調査・検討などを行う。また、さまざまな領域における調査・研究を基に、政策への提言を行うこともある。
▼2026年卒向け詳細情報▼
簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。
インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!
——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー
東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
——————————————————
※記事制作時の業界状況を基にしています
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。