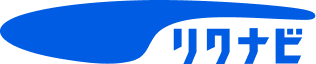日常生活の基盤となる設備やシステムを提供し、社会のライフラインの構築・維持をするのがインフラ業界です。世の中の支えとなるインフラ業界にはどのような仕事があるのか、詳しい事業分類や代表的な職種、今後の動向を解説します。
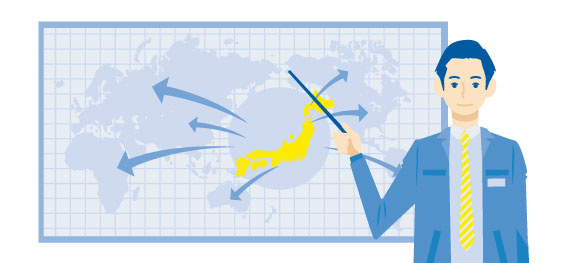
インフラ業界にはどのような分野がある?
インフラとは、「インフラストラクチャー(infrastructure)」の略語で、「下支えする」といった意味を持ちます。転じて、日々の暮らしや経済活動の基盤となる、社会に欠かせない設備や仕組み全般を指しています。そして自社の人材をはじめとした経営資源を基に、こうしたインフラを提供する事業を手がける企業を、インフラ業界に分類するのが一般的です。
インフラ業界の主な事業分類
インフラ業界で取り扱う事業には、幅広い種類が存在していますが、次のようなカテゴリー分けができます。
| 事業分類 | 取り扱い分野 | 業種例 |
|---|---|---|
| エネルギーインフラ | 電力ガス熱供給 | 発電所、変電所、ガス製造・供給所、暖冷房業 など |
| 生活インフラ | 上下水道通信廃棄物処理 | 浄水場、配水場、ポンプ場、下水処理場、固定電話通信、移動体通信(携帯電話)、インターネット・サービス・プロバイダー、清掃工場 など |
| 交通インフラ | 交通(移動手段) | 電車、バス、タクシー、空港、フェリー、高速道路整備 など |
| 空間インフラ | 公共施設土木 | 総合建設業・ゼネコン(学校、病院、文化施設 ほか)、土木工事業(堤防、護岸、ダム、貯水池、防波堤、桟橋、橋梁[(きょうりょう)]、水道、道路 ほか)など |
いずれも、身近な日常生活に深くかかわるサービスや施設などに携わる事業です。
インフラ業界に関連する職種
以下からは、インフラ業界で見られる主な職種を紹介します。なお具体的な業務内容は、取り扱い分野や企業ごとにさまざまです。もし気になる企業があれば、各社の採用ホームページなどから、職種の名称や業務内容の詳細をチェックしてみるとよいでしょう。
営業
個人または法人の顧客に対し、ニーズに応じた商品やサービスを提案するのが主な仕事です。例えばエネルギーインフラ・生活インフラなどの分野では、コスト削減・環境配慮・業務効率化というような、顧客のさまざまな要望や課題解決に向けた提案をします。そのほかにもオーダーに応じて必要なインフラ機器を届けたり、お客さまの近況に合わせて契約プランを変更したりするなど、既存の取引先も含めた顧客対応全般を担当します。なお公共団体と取引する際には、他社との価格競合から案件を受注する、入札担当を担うケースもあります。
マーケティング・企画
市場調査・分析をはじめ、販促計画の立案や新規商品・サービスの開発など、戦略的に業績アップを目指していくのが主な仕事です。例えば電力・ガス・インターネットなどを扱う企業では、自社の商品・サービスの認知度向上や購買促進に向けたプロモーション活動も含めて、さらなる事業成長を促す施策をプランニングしていきます。
エンジニア
施設・装置・システムなどの技術的な課題解決に向けた、製品設計・開発・構築・運用などを主に行います。具体例として、電気設備の施工をする電気工事士や、インフラ設備の設計・据え付け・メンテナンス・修理を手がけるフィールドエンジニアなどが挙げられます。生活インフラとなる通信分野では、サーバーやネットワークを構築するITエンジニアと呼ばれる職種もあります。
コンサルタント
さらなる生活向上のための課題や顧客のニーズを把握して分析し、必要なインフラ設備・施設を検討したり、より良いインフラの構築に向けた計画を立てたりするのが主な仕事です。例えば空間インフラとなる公共施設・土木分野では、土地の周辺調査や施工計画のプランニングなど、建設・工事を行うための企画を担います。また通信分野では、より効果的なネットワークや情報システムについての分析・提言を行うITコンサルタントが存在します。そのほかにも、電気使用の最適化を図る、電力分野のエネルギーコンサルタントなどの職種もあります。
施工管理・プロジェクトマネージャー
インフラの構築に伴う、現場作業を取りまとめる管理業務を主に担います。例えば公共施設・土木分野では、作業の工程管理・現場指揮・人材や資材発注といった、建設時のマネジメント全般を行う施工管理と呼ばれる職種があります。また通信分野では、ネットワーク構築に向けた作業全体の進捗(しんちょく)を管理する、プロジェクトマネージャーが存在します。いずれも、インフラを作り上げていく過程を統括する役割となります。
渉外
インフラの構築に向けて、各地域や政府・官公庁との交渉・調整をするのが主な仕事です。地域住民に向けて工事予定の概要を説明したり、自治体と連携して事業認可を得たり、国の機関に対してインフラ構築に関連する法規制などの政策提言をしたりするなど、プロジェクトを円滑に遂行させるための折衝を行います。
現業職
インフラに関連する現場において、さまざまなオペレーション業務を行います。例えば電力・ガス・上下水道・通信分野では、発電所・供給所・下水処理場・基地局など、各インフラ施設・設備を稼働させる現場作業が発生します。具体的には機械装置の操作・運転をしたり、点検・メンテナンスといった保守運用をしたりなどの仕事があります。また電力・ガス・上下水道分野では、顧客のインフラ使用状況を確認する検針業務なども行います。そのほかにも交通分野なら、車掌・運転士・キャビンアテンダント・パイロットをはじめとした乗務員や、整備士・駅務員・空港職員・運行管理など、現業職は多岐にわたります。
インフラ業界の今後の動向
インフラ業界は、社会全体の基盤を支える事業に携わるからこそ常に需要があり、安定性や貢献性が高く不況の影響も受けにくい傾向にあります。一方で、少子高齢化による国内市場の縮小やビジネスの担い手不足が大きな社会問題となっており、インフラ業界でも課題となっています。また世界的に環境意識が高まっている背景もあり、ビジネスとしてエネルギー供給に取り組んだり、多くのエネルギーを消費する事業を手がけるケースもあるインフラ業界では、エコやSDGsに対する施策も強く求められています。例えば、事業におけるエネルギー消費や二酸化炭素の排出量の抑制など、さまざまな対策がよりいっそう必要とされている状況もあります。
とはいえ、業界の抱える課題・現状に対応していくことで、さらなる発展を促すビジネスチャンスに期待する側面もあります。インフラ業界が発展を模索する動きとして、次のようなものが挙げられます。
世界的なインフラ整備の推進
持続可能な社会に向けて、国際的に注目されている「SDGs」の中では、世界各国、特に開発途上国を取り残すことなくインフラ整備を進める目標が設定されています。安全で便利な生活はもちろん、産業・技術革新を推進するインフラ普及を強化する方針となっており、水道や通信をはじめとした幅広い施設・設備が海外諸国でも求められています。こうした背景に加えて、国内では人口減少によるマーケットの先細りの影響もあり、インフラ業界全体として海外市場の有用性が高まっていく見込みです。今後は、海外におけるインフラ構築のニーズに対応すべく、国外進出を目指す企業も増えていくことが予想されます。
国内インフラの改良・強化のニーズが増加
各施設・設備の老朽化や自然災害に向けた対策として、インフラの補強・リニューアルが求められ、ニーズが増えてくる見込みがあります。一方で過疎化が進む地域では、費用対効果や人口減少の観点から、インフラの保全・更新が難しい現状もあります。そこで各分野では、こうした需要や課題への対策として、低コストかつ効率的なインフラ運用を図る取り組みにも力を注いでいます。具体例としては、各インフラの維持・メンテナンスにロボットやセンサーを取り入れるなど、IT導入による省力化・自動化が推進されています。例えば交通分野では、自動運転の導入を進め、運転士不足に対応しようとするなど、実際に世の中のニーズに対応すると同時に、ハイテクノロジー化を進める動きも見られます。
生活インフラ:最先端技術の積極的な活用
国内インフラの補強需要に加えて、少子高齢化による人手不足や急速な技術革新もあり、日常生活に身近な分野でもAI・IoT(※1)・ICT(※2)が積極的に取り入れられています。例えば、住宅内のエネルギー使用を管理できるシステムの導入などを通じ、エネルギー消費を抑制する動きも進んでおり、さまざまな生活サービスをITが下支えすることを受けて、通信インフラの需要も高まっています。こうした最先端技術の活用を通じて、今後もインフラ機能のさらなる向上が進んでいく見込みです。
※1 IoT:通信機能付き機器(スマートスピーカー、遠隔カメラ など)
※2 ICT:情報通信技術(クラウドサービス、SNS など)
エネルギーインフラ:再生可能エネルギーの供給強化
持続可能な社会を目指して世界的に取り組んでいる「SDGs」の中でも、資源を守るための施策として、再生可能エネルギーの導入が推奨されています。さらに一部の大手企業などでは、すべての使用電力を再生可能エネルギーに切り換える「RE100宣言」の施策も進められています。こうした背景から、特に電力・ガス分野では、再生可能エネルギー供給のニーズに対応する取り組みが積極的に推進されていく見込みです。
交通インフラ:鉄道事業の多軸化
交通分野では、テレワークの普及や自家用車の自動運転技術などの影響から、鉄道の利用頻度が低下する傾向も見られているのが現状です。そうした中でも今後の需要拡大を目指すべく、駅施設を有効に活用した、新たなサービスに乗り出す企業も出てきています。具体的には、身近に利用しやすい小売店の展開をはじめ、宅配取り次ぎや保育園送迎のサポートなどに取り組む事例があります。地域に密着した多角的な事業推進による、新たなニーズの創出にも期待されています。
【まとめ】インフラ業界では世の中に役立つ実感を持って活躍できる
インフラ業界では、エネルギー・生活・交通・空間といった、社会全体を支える幅広い事業を手がけています。いずれも日々の暮らしや経済活動を豊かにする社会的な基盤を築くビジネスであり、たくさんの人々の生活を支え、世の中に役立つ実感を持って活躍できる業界といえます。また国内では少子高齢化による厳しい現状があり、インフラ業界でも同様に大きな課題となっていますが、一方で新たな成長につながる動きも見られます。
インフラ業界に関するインターンシップやオープン・カンパニーに興味がある方は、リクナビをぜひチェックしてみてください。気になる業種ごとにインターンシップ&キャリア情報を調べることができます。

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。