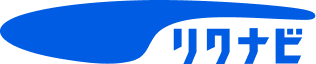信用金庫とは、地域に根差した協同組織型の金融機関です。営利を目的とせず、地域経済や中小企業を支える役割を重視しています。信用金庫と銀行の違いや仕事内容、信用金庫業界の最新トレンドなど、就活準備に役立つ情報を網羅しました。
信用金庫業界とは
信用金庫とは、お互いを支え合う「相互扶助」の精神の下で運営されている金融機関のことです。預金・融資・為替といったサービスを軸に、地域の経済インフラを支えています。
信用金庫は全国に240法人ほどあり、地域ごとに地元に密着した経営を行っています。中には、100店舗以上の店舗網を持つ京都中央信用金庫(京都府)や岡崎信用金庫(愛知県)のように、地域密着型でありながら一定の規模を備えている法人もあります。
信用金庫と銀行の違い
信用金庫と銀行は、どちらも預金・融資・為替といった金融サービスを通して社会を支えている点は同じです。ただ、組織の在り方が次のように異なります。
| 信用金庫 | 銀行 | |
|---|---|---|
| 組織形態 | 会員の出資による非営利法人 | 主に株式会社によって運営される営利法人 |
| 会員資格 | 地域内に住んでいる、または勤めている人※事業者の場合は、従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者 | なし |
| 主な取引先 | 地域の中小企業や個人 | 国内外の大手企業、国内の中堅・中小企業 |
| 業務範囲 | 預金…誰でも利用できる融資…原則として会員に融資する | 預金、融資ともに誰でも利用できる |
信用金庫の大きな特徴は、地域に縁がある会員の出資によって運営されているところです。
株式会社である銀行とは異なり、「会員同士がお互いに助け合うこと」に重きが置かれています。
例えば、銀行は自社事業の継続性や収益性を重視する傾向にありますが、信用金庫は地域の成長を支えていくことを大切にしています。地元の小規模事業への融資や、個人開業の資金支援など、収益面ではやや優先度が低いニーズにも幅広く対応するところが特徴です。
このように、信用金庫と銀行は業務内容が似ているものの、主な顧客層や融資のスタンスなどが異なります。信用金庫業界を志望する場合は、「どんな人々のために、どういったスタンスで働いているか」という点を意識して企業研究をしてみると良いでしょう。
信用金庫業界の業務内容
信用金庫は、会員から預かった資金を地域の中小企業や住民に融資するなどして、地域経済を支える役割を果たしています。こうした流れを実務として担っているのが、預金・融資・為替といった業務です。それぞれの業務内容を簡単にまとめました。
預金業務:地域の資金を集める
個人または企業から資金を預かり、管理します。信用金庫は基本的に会員のために活動している組織ですが、預金サービスについては会員以外でも利用することが可能です。集まった資金は主に、地域の中小企業や個人への融資に活用されます。
融資業務:中小企業や個人への資金提供
預金によって集めた資金を、会員である地域の中小企業や個人に融資します。比較的小規模な融資にも丁寧に向き合う風土があることから、地域の事業者にとって資金的な相談をしやすい存在といえます。
為替業務:振り込み・送金などを担う
振り込み・送金・口座振替といった、口座間の資金移動サービスを提供します。信用金庫同士はもとより、ほかの金融機関とも相互に資金を動かすことが可能です。
そのほかの業務
信用金庫は上記の3大業務のほかに、地域を支えるさまざまな業務を行っています。地方創生に向けた事業の支援や、地域の中小企業の事業承継サポート、新しい事業者の育成、地域イベントの協賛などが主な例です。
地域への貢献や発展に力を入れる信用金庫は多く、全国の信用金庫が会員となっている「全国信用金庫協会」でも、こうした取り組みを広くPRしています。1997年からは、地域に根差した活動で成果を上げた信用金庫に、「信用金庫社会貢献賞」を授与する取り組みもスタート。例えば第28回(2025年)の「信用金庫社会貢献賞・会長賞」には、オープンファクトリーイベントを通して区のものづくりの魅力を伝え続けている東京東信用金庫(東京都)が選ばれました。
信用金庫の地域貢献の様子を知りたい方は、全国信用金庫協会のHPもチェックしてみるとよいでしょう。
「信用金庫社会貢献賞」の創設、受賞活動の紹介
信用金庫の主な職種
信用金庫には、営業や窓口対応(テラー)、マネーアドバイザーといった幅広い仕事があります。いずれの仕事も、地域の企業や住民に寄り添う姿勢が求められる点が特徴です。
営業
営業は、地域の中小企業や個人宅を訪問し、融資や預金商品の提案を行う役割です。地域の方々や経営者の方々の悩みを丁寧にヒアリングし、資金面のサポートにつなげます。長い付き合いを前提にする場面も多く、顧客との信頼関係を築く力が求められるポジションです。
窓口対応(テラー)
来店した顧客に対応するポジションです。窓口にて入出金や振り込み、口座開設、公共料金の支払いといった、幅広い手続きを担います。地域に住む方々とのやりとりも多いことから、金融知識だけでなく、相手の気持ちをくみ取る力やコミュニケーション力が求められます。
融資担当
融資担当は、地域の中小企業や個人からの資金相談に際して財務状況を確認し、融資できるかどうかを判断するポジションです。人情で資金を貸すのではなく、相手の返済能力や事業の成長性に目を向ける姿勢が求められます。
経営支援
経営支援は、企業の課題に寄り添い、売り上げ改善や組織づくりといった事業面のアドバイスを行うポジションです。時には外部の専門家と協力しながら、市場動向の分析や人材育成の相談、取引先の紹介などにも取り組み、地域の中小企業の成長を後押しします。
マネーアドバイザー
マネーアドバイザーは、個人から寄せられる資産運用・相続・贈与といった相談に対応するポジションです。営業担当と連携しながら顧客の状況を丁寧に確認し、より良い資産づくりをサポートしています。
信用金庫業界の動向と今後の取り組み
地域経済と地方創生に大きく貢献している信用金庫業界は、今後も地域にとって欠かせない存在です。ただ、近年は人口減少や少子高齢化により、地域の過疎化が進んでいます。地域密着型のビジネスを続けてきた信用金庫にとっても、従来の「地域の中小企業や住民を支えていく」というビジネスモデルだけでは経営が難しくなっているのも事実です。
このような状況を受けて、信用金庫は中小企業にとって課題となりやすい人材育成や新規事業の立ち上げなどもサポートしながら、地域の活性化を支えています。そして、地元をけん引する企業を育てることで、将来の取引先の確保に努めています。加えて、以下のような取り組みも進められています。
近隣の信用金庫との合併
近年は、信用金庫同士が合併し、営業エリアを広げながら経営基盤を強化していく動きが見られます。合併によって事業規模が広がることで、融資の資金を確保しやすくなるほか、人員の最適化や業務の効率化も期待できるところがメリットです。
地域内で安定した金融サービスを提供し続けるため、今後も合併は重要な選択肢となっていくでしょう。
DXの推進
デジタル化の遅れが指摘されてきた信用金庫業界では、若年層の取り込みやNISA口座の開設が進みにくいという課題がありました。これを背景に、Web完結型のサービスの提供やペーパーレス化といったITサービスを導入し、利便性を高めようとする信用金庫が増えています。
加えて、オンライン型の金融サービスの実現に向けて、デジタル人材を育てようとする動きも顕著です。実際に、職員がIT系の資格を取得できるようサポートしたり、信金中央金庫が運営するeラーニングシステム「Sels(セルズ)」を介して、職員のITリテラシーの向上を図る信用金庫も珍しくありません。
今後も地域に寄り添う金融インフラであり続けるため、デジタルにも対応できる組織づくりが加速していくと考えられます。
SDGsへの取り組み
信用金庫は、地域経済の安定と発展にかかわるという役割から、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」というマインドと親和性が高い事業です。実際に地域課題をテーマにしたイベントの開催や、自治体・大学との連携など、多くの信用金庫でSDGsへの取り組みが行われています。
例えば、全国の信用金庫を支える中核的な機関として知られる信金中央金庫は、地方公共団体と信用金庫が連携して行っているさまざまなSDGs施策に寄付をしています。各信用金庫においても、地域の未来を担う学校などへの寄付がセットになった「しんきんSDGs私募債」を取り扱う法人も多いです。
まとめ
信用金庫は、地域の企業や住民と向き合いながら、金融サービスだけでなく地域の課題解決にも深くかかわっている金融機関です。地域の過疎化をはじめとする社会の変化に対応しつつ、合併やDX、SDGsといった新たな取り組みも進んでおり、役割はさらに広がりつつあります。
業界研究の際は日々のニュースにも目を通し、信用金庫の新しい動向を把握しておくとよいでしょう。信用金庫業界に関するインターンシップやオープン・カンパニーに興味がある方は、下記ページもぜひチェックしてみてください。

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。