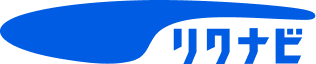(1)ファッション・服飾雑貨・繊維業界の概況
ファッション業界は、景気や天候等の影響で市場規模は増減する傾向があるが、中長期のトレンドとしては、人口減に加えて若年層の減少により、市場の縮小傾向が懸念されている。消費者の節約志向の高まりにSPA(後述)やファストファッション(後述)の低価格な衣料品がマッチしたため、一人当たりの衣料品への支出額が抑えられていることも一因と考えられる。
(2)ファッション・服飾雑貨・繊維業界の仕組み
衣料品や服飾品は、一般的にはまず、アパレルメーカーが商品の企画やデザインを行う。次に、商品に必要な素材を、専門商社などを通じて、素材メーカーと言われる原糸メーカーや、それを染色する企業、糸を生地にする繊維(織物)メーカーなどから調達する。そして、アパレルメーカーでデザインに沿って縫製されて商品になったものが、百貨店や小売店、通販会社などで販売される。
衣料品や服飾品は、複数の企業が分業して関わることが多いが、商品の企画から素材調達、製造、販売までを自社で手がける「SPA(Speciality store retailer of Private label Apparelの略。製造小売り)」という業態の企業もある。SPAは在庫を抱えるなどのリスクはあるものの、自社で製造することにより、コストを下げられる、独自性が出せる、市場の反応に素早く対応できる、などのメリットがある。最近では、SPA業態の企業が、素材メーカーと協働し、機能性に優れた高付加価値商品を開発するなどの取り組みも盛んだ。
流行を取り入れながら低価格に抑えた商品を、短いサイクルで大量生産・販売する「ファストファッション」もSPAの特徴を生かしたものの一つ。海外ではファストファッションを手がける企業も多く、日本国内でも20代女性を中心に支持を得ている。
宝飾品は原料(ダイヤモンドなど)の買い付け、商品の企画、デザイン、加工を経て販売される。原料の調達から販売までを行う企業、企画やデザインを発注して加工されたものを販売する企業、店頭販売だけを行う企業など、業態はさまざまだ。
衣料品や服飾品、宝飾品の販売は、百貨店や量販店、ショッピングモールなどの実店舗で行う場合と、カタログやテレビ、インターネットを通じてやりとりする通販とがある。
実店舗での販売では、訪日外国人対策が今後のカギとなる。政府は「2020年に訪日外国人旅行者数を4000万人にまで増やす」という目標を立てている。各企業・各店舗は、増え続ける訪日外国人に対応するために、外国語で接客できるスタッフの補充、外国語の案内を設置する、などの策を進めている。
インターネット通販では、一つのサイトで複数のブランドを取り扱うことで、Web上でショッピングモール化している総合サイトが急成長し、「インターネットで衣料品を買う」という購買行動の大きな流れを作っている。また、家具などの大型商品は、通販で買うと商品が自宅に配送してもらえるので消費者にとっての利便性も高く、今後も有望なチャネルだと考えらえる。
(3)ファッション・服飾雑貨・繊維業界のHot Topics
O2O
「O2O」とは、Online to Offlineの略。インターネット通販などオンラインで接点のあった顧客が、オフラインの実店舗にも足を運んでくれるようにすることを指す。例えば、インターネットで購入した人に店頭で使える割引クーポンを発行するなどの方法がある。背景にあるのは、インターネットで売り上げを高めるだけでなく、実店舗での売り上げ増加にもつなげていきたいという狙いがある。
機能性商品の開発
SPA業態の企業が、繊維メーカーなどの素材を扱うメーカーと共同開発した高付加価値商品に注目が集まっている。水で洗える紳士物のスーツ、衣服内の温度をコントロールする下着、着用時に動きやすいよう伸縮性を加えた衣料品などが代表的だ。
越境ECサイト
「越境EC」とは、インターネット通販サイトによる、国際的な電子商取引を指す。(ECとは、「Electronic Commerce」の略で、日本語に訳すと「電子商取引」。広義にはインターネット上での商品・サービスのやりとりをすることを指す)。
海外に住む人に向けて、日本製品を(日本から)販売する専用サイトの開発が盛んであり、越境ECは、今後の大きな成長分野である。経済産業省の報告書によると2015年時点で越境ECによるアメリカからの購入は5381億円、中国からの購入は7956億円と推計されている。特に中国からの購入は2019年には2兆3359億円という推計値もあり、今後もEC市場開拓のためのさまざまな取り組みがされていくだろう。
チャイナプラスワン
今までは、衣料品をはじめ服飾品などは、製造拠点を中国に置いていた企業が多かった。しかし、中国の人件費高騰や一国に集中するリスクを避けるために、最近はミャンマーやインドネシアなど、中国以外のASEAN諸国に生産拠点を持とうとする「チャイナプラスワン」という戦略をとる企業が増えている。
(4)関連業界とのつながり
百貨店
百貨店は、販売面での重要な関係先。アパレルメーカーが百貨店に商品を卸したり、販売を委託したりすることもあれば、アパレルメーカーが自社の販売店を百貨店内に出店させることもある。
専門商社
雑貨やアパレルを専門に扱う商社のほか、繊維の中でも毛織物に強い、シャツに特化しているなど専門分野を持つ商社も多数ある。
▼2026年卒向け詳細情報▼
簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。
インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!
——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー
東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。
——————————————————
※記事制作時の業界状況を基にしています
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。