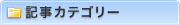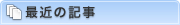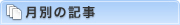本日も研修で学んだことについてお話していこうと思います。
午前の研修では、緊張を周囲に悟られないようにする手法について学習しました。
大抵の場合において周囲に緊張が伝わってしまう要因は「自身の行動」にあります。人は、手の震えや立ち上がる際の焦った様子、せわしない視線の動きなどを見ることで、相手が緊張していると判断しています。また、こうした行動によって緊張が相手に伝わってしまうと、自信のなさや準備不足、不信感などの負のイメージを相手に抱かせてしまい、途端に不利な状況へと陥ってしまいます。
このようなデメリットを持っている緊張ですが、それ自体を取り除くためには場数を踏むことで状況に慣れていく以外に方法がありません。
しかし、こうした「自身の行動」が周囲に緊張を示してしまうことにつながるのであれば、この行動の部分さえ隠してしまえば相手に緊張を悟られないようにすることが可能になります。幸いにして、手の震えや立ち上がる所作、視線の動きなどの動作も、少しの工夫によって隠したまま相手と接することが可能です。
自分も緊張してしまいがちな性格のため、この「行動さえ隠してしまえば気づかれない」という対処法は今後、大いに活用していきたく思います。
午後の研修では、データの正規化における分割手法と、実装可能性を検討する際に気を付けるべき点について学習しました。
データの正規化とは、データベースで管理する項目を決定する際、重複や無駄な項目を削減することで効率よく管理できるようにテーブルを整える手法のことを指します。
正規化には「非正規形」、「第一正規形」、「第二正規形」、「第三正規形」の四段階が存在し、各項目の導出性や他の項目との従属性、重複性などそれぞれ異なる基準によってテーブルの分割や項目の削除などを行うことで、データの管理を容易に行える形へと整理していきます。
正規化されたデータは、一見すると非常に使いやすい形のように思われますが、正規化によって管理するテーブル数が増加することがデメリットになるケースも存在しています。
例えば、正規化によってテーブル数が増えたことでデータ検索の際にテーブルを閲覧する回数が増え、メモリの使用量が増加することによって全体的なパフォーマンスが低下してしまうといったケースが予想されます。このようなケースにおいては、データベースに重複する項目や導出性のある項目を実装することで閲覧回数を減らすことができるなど、非正規化されたテーブルを使用することが解決策になります。
正規化はデータベースの管理を容易にし、重複や無駄を省くことが可能です。しかし、正規化されたデータベースが必ずしも要件に沿った形であるとは限りません。要件によっては非正規形のテーブルのほうが良い場合が存在します。
そのため、データベースにおける実装可能性の検討においては、要件の内容とパフォーマンスを常に意識し、時には正規化に固執しない発想を持っておくことが大切です。
ご覧いただきありがとうございました。
次回のブログもよろしくお願いいたします。