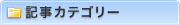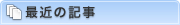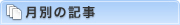おはようございます!
さて本日は、曜日について少し書いてみようと思います。
私たちは日々当たり前のように
月曜日~日曜日という習慣の中で過ごしていますが、
なぜそのような呼び方になったのかご存じでしょうか?
カレンダーで使われている7つの曜日は、
7つの惑星とそれらを象徴する神々が
1日を支配すると考えた古代都市バビロンの占星術の思想を発祥とします。
曜日の考え方は、メソポタミア地方から各地へ伝播し、
古代ギリシアでも各惑星と神話の神々とが対応しました。
その対応関係は古代ローマにおいても、
ギリシア神話の神々と同一視されたローマ神話の神々へそのまま受け継がれ、
ローマにおけるラテン語の曜日の呼称が現在へとつながっています。
ちなみに古代中国でも同様に7惑星から七曜の概念が生まれ、
遣唐使の頃に日本へ伝来したそうです。
そして日本語の場合、曜日と惑星の対応関係はとても分かりやすく、
日=太陽、月=月、火=火星、水=水星、木=木星、金=金星、土=土星 と
曜日の名前は太陽・月・惑星の名前に由来します。
では、なぜ曜日と惑星が関係しているのでしょうか?
昔の人々は規則的な動きをする夜空の星々から時間や季節を読み取っていました。
その星々の中で5つの星だけが星を追い越したり途中で引き返したりして
不思議な動き方をしていることを発見しました。
これらが惑う星「惑星」です。
5つの惑星は肉眼で見ることのできる水星、金星、火星、木星、土星でした。
現在、私たちはこれらの惑星が太陽を中心にまわっていることを知っていますが、
昔の人々は地球を中心に惑星や太陽、月が回っていると考えていました。
そして太陽、月、5つの惑星が時間や空間を支配すると考えていたのです。
このような由来から、曜日には惑星が関係しているのだそうです。
曜日の由来、皆さんはご存じでしたか?
私は全く知りませんでした(笑)
当たり前に使っている言葉でもなぜそうなのか分からないことってたくさんありますよね。
今は疑問に思ったことは調べればすぐに出てきますが、
昔の人の様々な気づきから今も使われている言葉が生まれていると思うと
なんだかすごいなと感心してしまいますね・・・(笑)