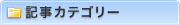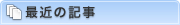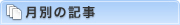1月18日に岡山県で開催された「強度行動障害のある人への支援をみんなで考えるシンポジウム~支援からの産物~」で基調講演の機会をいただいた。
強度行動障害支援者養成研修のプログラム作りを一緒にやってきた川西大吾さんのお誘い。
この研修会が他の強度行動障害に関する研修と違うところは、支援の「産物」をテーマにしているところ。
「産物」とは、今から30年以上前に支援が非常に難しい人たちの状態を「強度行動障害」と定義して、その支援方法や制度整備の推進を先導された飯田雅子先生の「行動障害の支援に携わった人は皆、産物を頂けます」という言葉から来ている。
強度行動障害のある人たちの支援は大変だというイメージがどうしても先行してしまうが、実際に支援をしている人たちの中には、大変さに向き合いながらも、強度行動障害のある人たち本人やその支援に魅力を感じている人たちも多い。
それは自分もこれまでの経験を通して感じてきたし、スタッフのみんなも感じることがあるように思う。
その魅力を取り上げて共有しようというところがさすが川西さんらしい。
私からは、これまで長くご本人やご家族と関わらせていただき、はるの生活介護やグループホームを利用されている方のエピソードを紹介した上で、自分が考える魅力を伝えさせてもらった。
「人として「素」なところに触れることができる」
ご本人はいい時も悪い時もストレート。
楽しい時やうれしい時は最高の笑顔を見せてくれたり、きつい時は激しい行動で気持ちを表してくれたり。
自分たちはいつもいろんなことを考えてしまい、あんなにストレートに自分の気持ちを表現することはできないので、いいなぁと思うことも。
「何気ない仕草や表情、行動のパワー」
強度行動障害があると言っても、24時間365日激しい行動をされているわけではない。穏やかな時のご本人の何気ない仕草や表情、クスっとするような思いがけない行動などに楽しさやうれしさを感じたり、癒されたり。
そんな時は私たちの気持ちを満たしてくれるご本人のパワーを感じる。
「支援の達成感」
支援が困難だからこそ、うまくいったときの達成感は大きい。
トイレを失敗せずにできた…、検温をできるようになった…、そんな些細なことに見えるようなことも、それができるように支援を考えて試行錯誤してきた支援者にとっては大きなことなのだ。
生活のちょっとしたことを喜ぶことができるって、すごく豊かなことではないかと思う。
「福祉の原点」
そもそも福祉は社会で困っている人たちを何とかしたいというもの。
ご本人やご家族、支援者の困り感がとても大きく、社会的な課題である強度行動障害への支援は、まさに福祉の原点ではないか。
だからこそ、関わっている人たちは福祉のスピリットや支援のやりがいを感じることができる。
研修のシンポジウムでも「産物」について取り上げられたが、岡山でがんばっているお二人の発表や発言がステキでとても勉強になった。
シンポジウムの中で会場の参加者からこんな質問が出た。
「支援が大変だった時にどうやって乗り越えましたか?」
その質問に対して、発表されたお二人と自分の返事は図らずも同じだった。
「周りの人たちに助けられた。」
具体的な支援方法であれ、気持ちのフォローであれ、自分たちの事業所や法人を越えたつながりが、強度行動障害のある人たちを支援するうえでは欠かせないとあらためて感じたやり取りだった。