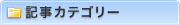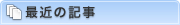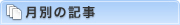どうにかならないかなぁと思うことがある。
最近、はるの一つの部署のミーティングでこのような話があった。
これまで行政から受けていた仕事があったが、今後はいろいろな福祉事業所にもやってほしいということで来年度から入札することになったそう。
はるとしてその入札にどう関わるか、という話。
この話を聞いて、前から思っていた疑問がまた湧いてきた。
入札と同じような仕組みとして見積り合わせもあるが、当然のことながら入札や見積り合わせは金額が低いところが契約をする権利を得ることが多い。
福祉事業所にとっては、これらの仕事から得る収入は障害のある人たちに支払う原資になる。
低い金額で仕事を受けると必然的に障害のある人たちに支払う金額が低くなる。
B型や生活介護では、利用者の皆さんに支払う工賃が低くなるということ。
今回のはるの件だけでなく、ふくしネットで取り組んでいる工賃向上の取り組みの中でも公官庁の仕事が見積り合わせのときがあり、低い金額で契約されるのを見るたびに何かおかしいと思ってきた。
仕事を受ける福祉事業所のほうも、ただ仕事を受けたいために、きちんと積算せずに極端に低い金額で見積もりを出すところがある。
このような無知なのかモラルハザードなのか分からないようなことは、福祉事業所の側として防止に取り組まなければいけない。
(福祉事業所では、低い金額で仕事を請け負っても、障害のある人たちの工賃は下がるが職員の給料は直接的には下がらないので、職員の危機意識が低いという指摘もある。)
しかし、そもそも公官庁では、障害のある人たちにできる仕事をできるだけ障害のある人たちにやってもらうことで、障害のある人たちの収入を上げていこうという優先調達推進法という法律もある。
それなのに、障害のある人たちが関わる仕事に入札や見積り合わせの仕組みを当てはめるのはどうしてだろう。
今回はそんな思いを自分だけで留めることができず、いつも親身に相談に乗ってくれる行政の役職付きの方のところに話しに行った。
その方は、しっかり私の話を受け止めてくれたうえで、このようなことを教えてくれた。
行政が特定のところではなくいくつかの福祉事業所に関わってもらい業務を委託するためには、仕組みとして入札や見積り合わせを実施せざるを得ない。
業務の内容によってはプロポーザル形式もあるが、プロポーザルはかなり手間がかかるので、少額の業務はなかなかそこまでできないのが実情。
とても重要なことではあるが、自分たちとしても悩ましいところ。
仕事を出す側も受ける側も悩んでいるこのことは、いったい何がハードルになんだろう。
いろいろな福祉事業所が関わって行政の仕事を受けることは、公益でもあり、公平でもある。
そのなかで、必要以上に低い価格でのやり取りをすることを防ぐためにはどうすればいいか。
福祉事業所の知識やモラルを上げていくだけでなく、行政の仕組みの中で工夫する余地はないのだろうか。
社会福祉法人はる
理事長 福島龍三郎
「りゅうさぶろぐ」より
気になった方は以下をチェック!