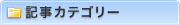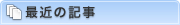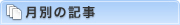少し前になるが、今年もSANC主催でスター発掘プロジェクトを開催した。
自分もすごく楽しみにしているイベントだが、今年は別の研修が入って最後の3組ぐらいのパフォーマンスに滑り込みで駆け付けた。
会場の入り口で、いつも強度行動障害の研修でお世話になっている施設職員のKさんと会って言葉を交わすと、Kさんはおもむろに涙を浮かべて施設利用者の方がステージでパフォーマンスができたことのよろこびを伝えてくれた。
イベントが終わって、今回初めてコメンテーターをお願いした大学の美術教員のH先生にお礼に行くと、放心したような表情で「よかった」と言われていた。後日開催した協力委員会でイベントを振り返ったときにも「思い出しただけで涙が出る」と言われていた。
会場に入ると、言葉には言い表しにくいのだが、会場全体がとても温かく感じた。
ステージでパフォーマンスをする人も、コメンテーターとしてコメントをしてくれる人も、会場で応援している人も、ただ見ている人も、別々ではなくつながっている感じがした。
とても心地いい感じ。
後日、映像で出演した皆さんのパフォーマンスを見たが、それぞれ思い思いのパフォーマンスが披露されていた。
歌もあれば、演奏もあれば、ダンスもあれば、漫才もあれば、腹筋もある。
緊張もあれば、マイペースもあれば、ドタバタもあれば、感動もある。
そこは一番を目指したり評価を得るためではなく、とにかく自分たちがやりたいこと、見てほしいことをやるステージ。
そんなステージが何故こんなに心地よかったり感動したりするのだろう。
人はなかなか在りのままでいられない。
普段は世間体や立場や人間関係のなかで自然と飾ったり気を張って過ごしている。
そんな中で、ただ自分たちがやりたいこと、見てもらいたいことを表現している姿に、何かしら琴線に触れるものがあるのかもしれない。
スター発掘プロジェクトは、ステージに立つまでの物語も含めてのもの。
パフォーマンスに込めた思い、準備や練習のエピソード、心の変遷、人生のヒストリー。
いろんな経緯があって目の前のパフォーマンスが披露されている。
そして、ステージに立つ人たちだけでなく、一人ひとりのパフォーマンスにはそれぞれの家族や友だち、先生や支援者たちの関わりや気持ちもつながっている。
Kさんが涙を浮かべたのは、ステージに立った利用者の方のことを普段からとても大切にされていて、これまで共に歩んできたたくさんの時間があるからだろう。
人が表現をすることは、本来はとても自然で、身近なものだと思う。
自分がやりたいことを表現したり、一緒によろこぶことが、どんなにそれぞれの人生に彩りを加えるだろう。
このスター発掘プロジェクトを企画してくれているのが小松原さん。
小松原さんとSANCスタッフの大石のインタビューは以下より。
来年のスター発掘プロジェクトがもう楽しみだ。
社会福祉法人はる
理事長 福島龍三郎
「りゅうさぶろぐ」より
気になった方は以下をチェック!